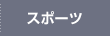<キャンパる>上智短大が3月末閉校 どうなる外国籍児童らへの日本語学習支援
上智大学短期大学部(神奈川県秦野市)は1988年から、同市と近隣に住む外国籍の子どもたちやその家族に対して無償で日本語学習や教科学習の支援を行ってきた。しかし、このプログラムが2026年度以降も続けられるか不透明な状況になっている。同校が今年3月末で閉校するからだ。開始以来、これまで400以上の外国籍家族を支援してきたプログラムの行方が注目されている。【上智大・平野恵理(キャンパる編集部)】
◇信頼関係がもたらす笑顔
昨年12月16日、秦野市内の公共施設「はだのこども館」で、上智短大の学生4人と職員2人、そして学習支援を受けている4歳から中学2年生の外国籍の子ども14人が参加して、年末恒例の「お楽しみ会」が開催された。
和気あいあいとした雰囲気の中、子どもらは塗り絵をしたり、日本語で合唱したり、学生から手紙を受け取ったりした。秦野ロータリークラブからも有志の会員が出席し、子どもらにクリスマスプレゼントを手渡した。
南米にルーツを持つ子どもらが多く、スペイン語と日本語を交ぜて会話をしたり、新しく引っ越してきたばかりのメンバーと日本人学生との間に入って、通訳をしたりする姿も見られた。
子どもらが上智短大の学生ら支援者に示す親しみや信頼感には、確固とした裏付けがある。このプログラムに参加する学生は普段、自ら毎週小学校・中学校に赴く出張型の支援と、外国籍の幼児から高校生、その家族を公共施設でサポートする二つの形態で学習支援をしている。
◇有志の活動から正規科目へ
支援対象の子どもの年齢は限定せず、学生たちは日本語学習や教科学習のサポートに加え、奨学金の書類作成から受験勉強の手助けまで、進学に必要な準備の支援にも幅広く対応しているという。支援プログラムを統括する上智短大英語科の宮崎幸江教授(64)は、「私たちは支援が必要な子どもたち一人一人に支援をする。サポートが必要な人がいれば、何人でも受け入れる。子どもたちがありのままの自分を受け入れてくれる日本人がいることを知って、日本人を好きになる経験をしてほしい」と語った。
30年以上、上智短大の職員と学生の有志がボランティアで行ってきたこのプログラムは、19年から講義と実習で構成される「サービスラーニング」として、参加学生に単位を付与できる同校の正規科目となった。
今学期、公共施設で日本語学習支援に取り組む中心メンバーは5人。メンバー1人あたり3人の子どもの面倒を見ているという。宮崎教授が受け持つ授業「サービスラーニング」の履修者が中心だが、短大の卒業生や、同じ経営母体「上智学院」の傘下にある4年制の上智大学の四谷キャンパス(東京都千代田区)から参加する学生も珍しくない。宮崎教授が同キャンパスで受け持つ授業でボランティアを募っているためで、ポルトガル語やスペイン語などの外国語や、多文化共生を専攻する学生のほか、修士課程や博士課程に在籍する大学院生も活動の輪に加わることがあるという。
上智短大から上智大学に編入学した霜鳥甘奈さん(23)は、同短大在学時に教育に関心を持ち、サービスラーニングを受講するようになった。上智大に編入学後も「短大生時代から面倒を見てきた子どもが心配」で、現在も四谷キャンパスから片道1時間半かけて、秦野での支援活動に参加しているという。
◇孤立解消の願いが原点
上智短大によると、同校で日本語支援が始まったきっかけは、インドシナ難民の受け入れに伴い発生した事件だった。日本は78年から05年にかけて、ベトナム、ラオス、カンボジア3国から1万人を超える難民を受け入れ、秦野市もその受け皿を担ってきた。
しかし、87年に同市内に住むカンボジア人難民男性による、妻と3人の子どもたちの殺害事件が発生した。男性は慣れない日本での生活下で孤立し、精神的に追い込まれていたことが原因と言われている。
当時、上智短大にスペインの聖マリア修道女会から教授として派遣されていたシスター・コルテスは、日本で暮らす難民が直面する問題が地域社会で共有されていないことに危機意識を持った。秦野市役所に「何かできることはないか」と直談判に行ったという。「自分たちが日本という新しい地で生活することの苦労を知っていたから、相手の気持ちがわかったのだと思う」と宮崎教授は推測する。
この事件の翌年から、上智学院が掲げる「他者のために、他者とともに」の教育理念のもと、有志の学生たちが外国籍家族のもとに出かけて、家庭教師ボランティアを開始。またシスターたちは上智短大と訪問先の家庭との信頼関係のパイプの構築に尽力した。
その後、90年に行われた出入国管理及び難民認定法の改正により、日系2世・3世とその家族の在留資格が新設された。これにより、金属製品など製造業の生産拠点が集まる秦野市にも、ブラジルやペルー、ボリビアからの移住家族が増え、日本語学習支援のニーズは高まっていった。上智短大はこの動きに対応し、子どもらへの学習支援の取り組みを拡充させてきた。
学習支援の場は、子どもらにとって学びの場であると同時に、貴重な居場所になっている。宮崎教授は「外国籍の子たちは、普段通う学校では話しづらいルーツを共有することができる」と言い、「普段の学校ではマジョリティーの中に埋もれているが、日本語教室ではのびのびとしている」と指摘した。
◇まいた種は育つか
ただ、支援活動を推進してきた上智短大は、少子化や女子学生の共学・4年制志向を背景に23年、24年度以降学生募集を停止することを発表した。閉校後を見据えたサービスラーニングの継続方法についても、検討が進められてきた。24年度から実験的に2年間、四谷キャンパスの学生に秦野の活動に参加してもらう「ソフィア日本語プロジェクト」を試行した。しかし最終的に「今と同じ形で残すことはできないと判断した」(宮崎教授)といい、上智短大としての秦野での支援活動は実質的に終了することになる。
上智短大が閉校し、秦野での支援の取り組みがなくなってしまうことは子どもたちにも伝えられている。12月の「お楽しみ会」に弟とともに参加したペルー出身のシルバナツミさん(14)は流ちょうな日本語で「とても悲しい。分かり合える友達ができて、続けやすい」環境だったと話した。ナツミさんは3年間、学習支援を受けていた。
一方で、来年度以降四谷キャンパスを拠点に都内で上智短大と同様の活動ができないかという模索も続いている。宮崎教授は「秦野でセーフティーネットがなくなってしまうことには不安はある」と語る一方、「これまで形を変えて日本語学習支援のコミュニティーは存続してきたから、きっと大丈夫」と話す。秦野市教育委員会との間で日本語教育をめぐる問題意識が十分に共有されていることや、市内に日本語教室が複数存在していること、秦野に住む外国人家庭を支える文化の蓄積があることを理由に挙げた。
例えば、上智短大職員の山崎菜津紀さん(26)は、日系ブラジル人というルーツを持つ。上智短大の卒業生で、宮崎教授の教え子だった。かつては日本語支援を受ける側だったが、現在は行う側に回って活動してきた。
上智短大がまいた共生に向けた種は秦野の地でどう継承されていくのか。そして、上智として日本語学習支援活動の精神をどう受け継いでいくのか注目される。グローバル化が進む一方で移民の受け入れ反対を叫ぶ排外的な主張が国内外で高まっている今、異文化との向き合い方が改めて問われている。
-
「分布拡大防止ライン」も突破 キョン生息域拡大、千葉県が対策強化
千葉県南を中心に農作物被害などを引き起こしている特定外来生物「キョン」への対応を強化するため、県が第3次の防除実施計画案を作成した。3月までに内容を詰めて正式…社 会 2時間前 毎日新聞
-
危険なヒグマ出没後は速やかに登山道閉鎖を検討 知床で再発防止策
世界自然遺産・知床の羅臼岳で昨年8月に登山客がヒグマに襲われて死亡した事故を検証している環境省や地元自治体などでつくる「知床ヒグマ対策連絡会議」は12日、人に…社 会 15時間前 毎日新聞
-
札幌・脱輪事故 被害女児の父「やはり」 執行猶予中に無免許運転か
札幌市で2023年11月、運転する改造車の車輪が外れ、女児に直撃させたとして札幌地裁から懲役3年、執行猶予5年の判決を受けた同市の自称重機オペレーター、若本豊…社 会 15時間前 毎日新聞
-
大阪府・市、万博跡地に記念館を建設へ 周辺一帯を「記念公園」に
大阪府と大阪市は12日、大阪・関西万博が開かれた同市の人工島・夢洲(ゆめしま)(此花区)に万博の記憶を後世に伝える記念館を建設する方針を決めた。一部保存が決ま…社 会 15時間前 毎日新聞
-
本因坊戦トーナメント1回戦 前期挑戦者の芝野十段が敗れる
囲碁の第81期本因坊戦本戦トーナメント(毎日新聞社など主催)1回戦が12日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、河野臨九段(45)が芝野虎丸十段(26)に232…社 会 15時間前 毎日新聞
 サイトマップ
サイトマップ